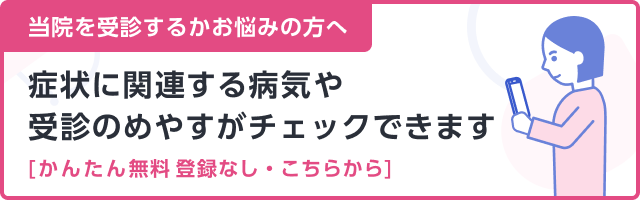潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎について | 奈良市の江川内科消化器内科医院
潰瘍性大腸炎とは

-
潰瘍性大腸炎は、大腸の内側に慢性的な炎症が起こり、潰瘍やびらんを引き起こす病気です。この病気は炎症性腸疾患(IBD)の一種であり、「クローン病」と並んで広く知られています。
日本では難病として認定されており、推定患者数は10万人に100人程度です。男女差はなく、若い世代から高齢者まで広範囲にわたって発症します。近年ではその頻度が増加傾向にあります。
潰瘍性大腸炎の炎症は通常、直腸から始まり、口側に広がる傾向があります。この病気は病変の場所によって直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型に分類されます。
症状には下痢や血便、腹痛、しぶり腹(便意があるが排便できない、または少量の排便)、重症化すると発熱、体重減少、貧血などの全身的な症状が現れることがあります。
原因ははっきりしていませんが、適切な治療により症状を抑えることができ、ほとんどの患者は健康な人と同様の日常生活を送ることができます。ただし、発症から7~8年以上経過すると、大腸がんを併発するリスクが増加するため、注意が必要です。
潰瘍性大腸炎の原因
潰瘍性大腸炎の原因ははっきりと特定されておらず、その治療には至る治療法も存在しないため、難病と見なされています。
潰瘍性大腸炎は、家族内での発症例も多く見られるため、遺伝的要因が関与している可能性が指摘されています。
また、食生活の乱れによる腸内環境の変化や、自己の大腸粘膜を攻撃する免疫の異常などが原因とされています。
潰瘍性大腸炎の症状
潰瘍性大腸炎の症状には、下痢や腹痛、血便などが含まれます。病状が悪化すると、発熱や体重減少、貧血などの全身的な症状が見られることもあります。
炎症の程度や大腸の炎症がどの部位にあるかによって、症状やその強さが異なります。潰瘍性大腸炎では血便が多く見られることがありますが、クローン病ではそうではないことがあります。
症状の現れ方には様々なパターンがあり、時には症状が繰り返したり、一定の状態が持続したり、急激に悪化することもあります。
また、口内潰瘍、眼の炎症、関節痛、皮膚炎など、腸以外の部位にも合併症が現れることがあります。
潰瘍性大腸炎の治療
薬物治療
潰瘍性大腸炎の治療には、まず薬物治療が主体となります。炎症の程度や症状に応じて、5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫調整薬、免疫抑制剤、生物学的製剤などが選択されます。直腸病変が軽度の場合には、局所療法として坐剤や注腸製剤が用いられることもあります。
症状や粘膜の改善具合、副作用などを観察しながら治療が進められていきますが、一旦よくなっても再発を繰り返しやすいため、薬が中止できずに継続が必要なケースも多くあります。
血球成分吸着除去療法
血球成分吸着除去療法は、薬物治療が有効でない場合や副作用が問題となる場合に検討されます。
これは、血液から炎症に関与する成分を除去し、再び体内に戻す方法です。
手術
近年の薬物治療などの進歩により手術が必要な患者様は減少傾向にありますが、治療が効果的でない場合や、副作用が深刻な場合には手術が検討されることもあります。
消化器疾患でお困りごとは当院へ
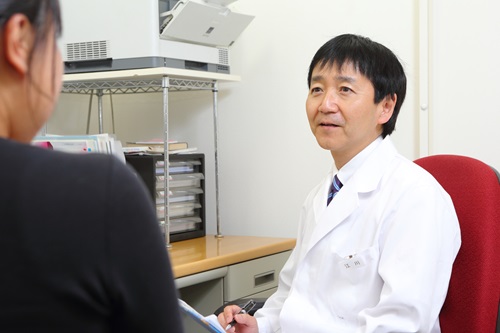
-
奈良市の江川消化器内科医院は、ひとりでも多くの患者さんの病気の早期発見・治療し、健康で充実した人生をサポートする医療機関を目指しております。
日本内科学会認定内科専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医の医師が、丁寧かつ正確に診断を行い、適切な治療を行います。消化器の症状でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。