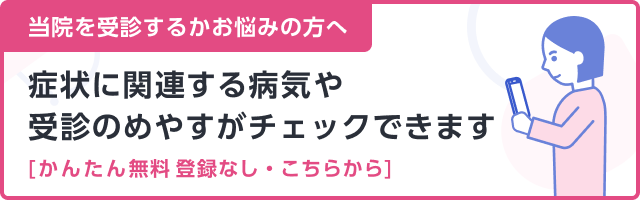過敏性腸症候群
過敏性腸症候群について | 奈良市の江川内科消化器内科医院
過敏性腸症候群とは

-
過敏性腸症候群(IBS)は、精神的なストレスや自律神経の不均衡などが原因で腸の機能に異常が生じ、便秘や下痢、腹痛などの排便異常を引き起こす病気です。大腸の検査をしても目に見える異常はないため、症状は主に患者の主観によって診断されます。
排便異常は個人によって異なり、持続的な下痢や便秘、またはその交互の繰り返しを経験することがあります。腹痛や腹部の不快感が伴うことも一般的で、症状の重さによっては日常生活に支障をきたすこともあります。
過敏性腸症候群は一般的な疾患であり、人口の約10%がこの病気に罹患しているとされています。
過敏性腸症候群の原因
現在のところ、過敏性腸症候群の発症メカニズムは完全に解明されていません。
腸の機能は脳と密接に関連しており、ストレスや心身の負担がトリガーとなって、腸の感覚過敏が引き起こされることが考えられています。
腸は自律神経によって調節されており、交感神経と副交感神経がその働きを制御しています。
交感神経は腸の運動を抑制し、副交感神経は腸の運動を促進します。
しかし、ストレスや疲労などの要因により、この自律神経のバランスが崩れると、腸の運動に異常が生じ、下痢や便秘が発生しやすくなります。また、腸の感覚過敏も起こり、腹部の不快感や腹痛を感じやすくなるとされています。
過敏性腸症候群とストレス
精神的なストレスが高まる状況下、例えば通勤や試験前などでは、急におなかが痛くなったり、下痢や便秘に悩まされることがあります。このようなストレスの強い人ほど、過敏性腸症候群の症状が顕著に現れると考えられています。
さらに、体調の変化が新たなストレス源となり得ます。たとえば、電車内での突然のおなかの痛みや、大事なイベント中にトイレを我慢しなければならないといった状況は、ストレスを増大させます。
過敏性腸症候群の患者は、痛みに対して過敏になっているため、些細な刺激でも腸が反応し、便通の異常や激しい腹痛などの症状を引き起こすことがあります。
さらに、心理的なストレスだけでなく、気温の変化や騒音、疲労などもストレスの原因となり得ます。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群は、お腹の不快感や痛みに加えて、便通に異常が生じる症状を伴います。
症状の現れ方や重さは個人によって異なりますが、一般的に以下の3つのタイプに分類されます。
下痢型
ストレスや緊張などのわずかな刺激で、お腹の痛みや強い便意と共に下痢が生じます。特にトイレに行けない状況下で発症しやすいとされます。
便秘型
便秘が続き、お腹の張りなどの症状が現れます。
混合型
便秘と下痢が交互に現れる特徴があります。
これらの症状が3ヶ月以上続く場合、過敏性腸症候群が疑われます。
どのタイプの場合も、ストレスや疲れが増すと症状が悪化しやすく、就寝時や休日には症状が軽減されることがあります。
また、排便すると一時的に症状が改善することも特徴的です。
過敏性腸症候群の検査・診断
過敏性腸症候群は、特徴的なお腹の症状や便通異常が見られるため、診断には問診だけで行われることもあります。
しかし、症状が重い場合や治療が効果的でない場合、腸の病気の可能性があるため、血液検査、便潜血検査、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)などの検査が行われることもあります。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群の治療は、ストレスや生活習慣と密接に関連しています。規則正しい生活習慣を整え、適度な食事やストレスを蓄積させないよう心がけることが重要です。
薬物治療では、整腸薬や腸管の働きを調整する薬を使用したり、下痢や便秘、腹痛に対して適切な薬物を組み合わせて処方されます。通常の薬物治療が効果的でない場合は、抗不安薬や抗うつ薬などの精神的な薬が使用されることもあります。
消化器疾患でお困りごとは当院へ
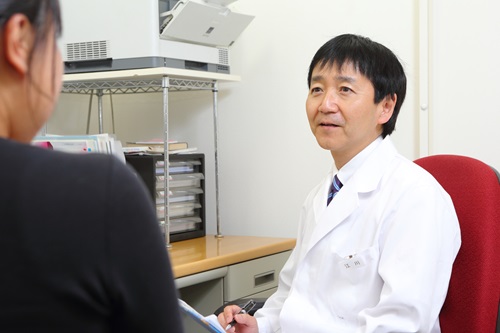
-
奈良市の江川消化器内科医院は、ひとりでも多くの患者さんの病気の早期発見・治療し、健康で充実した人生をサポートする医療機関を目指しております。
日本内科学会認定内科専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医の医師が、丁寧かつ正確に診断を行い、適切な治療を行います。消化器の症状でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。