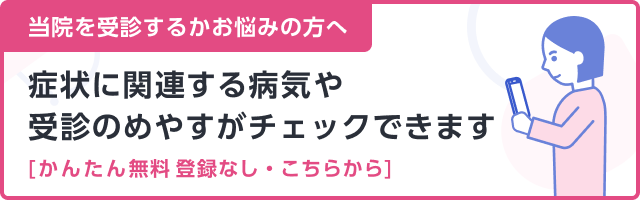便秘
便秘について | 奈良市の江川内科消化器内科医院
便秘とは

-
便秘は、単に「便が出ないこと」ではなく、毎日排便があっても排便が満足な状態ではない場合を指します。
日本消化器病学会関連研究会が2017年末に便秘の定義として発表した「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」に基づいています。
便秘の症状には、腸内に不必要な便がたまり、排便に過度のいきみが必要な排便困難や、腹痛や残便感が続くことが含まれます。
この状態は非常に一般的で、20歳から60歳までの間では女性の方がより多く見られますが、60歳を過ぎると男女差が少なくなり、年齢が上がるにつれて罹患率が増加する傾向にあります。
便秘の種類
便秘には大きく分けて4つのタイプがあります。
機能性便秘
最も一般的な便秘で、生活習慣やストレス、加齢などの影響により、大腸や直腸、肛門の機能が乱れることで起こります。
弛緩性便秘
腸管の緊張がゆるみ、ぜん動運動が不十分になることで大腸内に便が長くとどまり、水分が過剰に吸収されて硬くなるタイプです。頻度が高く、おなかが張る、残便感、食欲低下、肩こり、イライラなどの症状が見られます。
けいれん性便秘
副交感神経の過度の興奮により腸管が緊張しすぎ、便がうまく運ばれずに、コロコロとした便になるタイプです。食後に下腹部痛、残便感などの症状があることもあります。
直腸性便秘
直腸に便が停滞し、排便反射が起こらず排便できなくなるタイプです。高齢者や寝たきりの人、痔や恥ずかしさにより排便を我慢する習慣がある人に多いです。
器質性便秘
腸管の物理的な障害や状態により便の通貨障害が起こる便秘症です。大腸がんや腸管の癒着、炎症性腸疾患などが原因となります。
症候性便秘
全身疾患に伴うホルモン分泌異常や神経系の異常により腸管の運動が弱くなり、便秘が起こります。糖尿病や甲状腺疾患、脳血管障害などが原因です。
薬剤性便秘
各種の薬による副作用で起こる便秘症です。抗うつ薬や抗コリン薬、咳止めなどが大腸の運動を抑えるため、副作用として便秘が生じることがあります。
便秘の治療
便秘の治療には、以下の方法があります。
生活習慣の改善
- 食物繊維の積極的な摂取
野菜や果物、穀物などの食物繊維を十分に摂取することが重要です。 - 規則正しい食生活
朝食をしっかり摂ることや、食事の時間を守ることで消化器官のリズムを整えます。 - 適度な運動
日常的な運動やウォーキングなどの身体活動は腸の運動を促進し、便秘を解消します。 - 正しい排便習慣を身につける
便意を感じたらすぐにトイレに行くことや、朝は早めに起きて水を飲んでからゆっくり過ごすことが重要です。
薬物療法
- 下剤
便秘を一時的に解消するための薬剤です。短期間の使用に適しています。 - 大腸機能を促進させる薬剤
蠕動運動を活発化させる薬剤や、腸内細菌叢を改善する薬剤があります。 - 漢方
漢方薬には便秘に有効なものもあります。
消化器疾患でお困りごとは当院へ
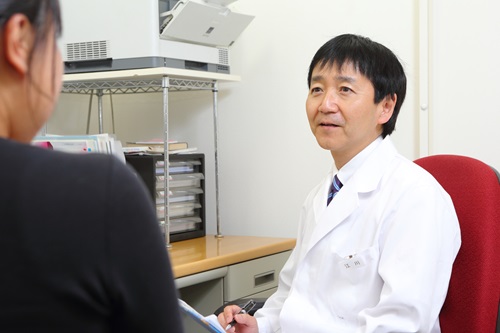
-
奈良市の江川消化器内科医院は、ひとりでも多くの患者さんの病気の早期発見・治療し、健康で充実した人生をサポートする医療機関を目指しております。
日本内科学会認定内科専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医の医師が、丁寧かつ正確に診断を行い、適切な治療を行います。消化器の症状でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。