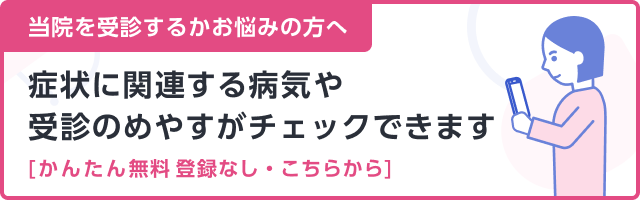血便
血便について | 奈良市の江川内科消化器内科医院
血便とは

-
血便には、赤いものが混じっている血便と、黒いタール便の2つのタイプがあります。
肉眼的血便は肉眼で血液が見られるものであり、顕微鏡的血便は便潜血検査で初めて検出されるものです。
肛門に近い場所からの出血は鮮やかな赤色を呈し、遠くなるにつれて黒っぽくなります。
原因は痔などの良性疾患からがんまで多岐にわたります。血便や下血は消化管のどこかからの出血によるものであり、出血箇所や程度、原因を特定して、適切な治療を行うことが重要です。
血便の原因
血便を引き起こす可能性のある部位は、肛門、直腸、大腸、小腸、胃、十二指腸など広範囲にわたります。
鮮やかな色の血便は、痔が原因によるものもありますが、直腸にできた大腸がんなど重篤な疾患によっても生じる可能性があります。
また、難病指定されている潰瘍性大腸炎やクローン病などでも血便が見られることがあります。
いぼ痔、切れ痔
排便時に出血して血便が生じることがあります。
この血便は鮮やかな赤色の血液が便に混ざるか、便器や拭いたトイレットペーパーに血が付着することがあります。
大腸がん
初期段階では、自覚症状がほとんどなく、がんが進行すると便中に血が混じり、血便として現れることがあります。
がんの組織は壊れやすく、周囲の血管を集める傾向があるため、進行すると持続的に出血しやすくなり、その結果として黒っぽい色合いのタール便として現れることもあります。
大腸ポリープ
大腸ポリープも血便の原因となります。良性であっても将来的にがん化するリスクがあります。
血便の原因を特定するための大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)で大腸ポリープが見つかった場合は、その場で切除することも可能です。
潰瘍性大腸炎・クローン病
潰瘍性大腸炎やクローン病も、血便を引き起こす可能性があります。
これらの疾患は炎症が活動期と寛解期を繰り返す特徴があり、活動期に血便が生じることがあります。
虚血性腸炎
左下腹部の激しい腹痛を伴い、血便が生じることがよくあります。
便秘時の強いいきみや動脈硬化による血管の狭窄や閉塞などが原因で、大腸の一部に血液供給が不足し、虚血状態が生じます。
この状態が炎症や壊死を引き起こし、血便を生じる原因となります。
軽度の場合は安静にしていれば症状が改善することもありますが、状態が重篤な場合は手術が必要となることもあります。
細菌性腸炎
細菌による感染が原因で引き起こされる疾患であり、この状態でも血便を生じることがあります。
細菌性腸炎の原因となる細菌には、カンピロバクター、サルモネラ、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌などがあります。
血便の他にも、腹痛、下痢、発熱、嘔吐などの症状も見られることがあります。
細菌性腸炎が疑われる場合は、抗生物質による治療が一般的に有効です。
胃・十二指腸潰瘍
粘膜が深く傷ついているため、出血することがよくあります。
その他にも、みぞおち周辺の痛み、げっぷ、胸焼け、吐き気、胃もたれなどの症状が見られます。
出血によって真っ黒いタール便という下血が生じることもあり、吐血することもあります。
このような症状が見られた場合は、放置すると貧血や穿孔などの合併症が生じる可能性があるため、できるだけ早く消化器内科を受診してください。
血便の検査
直腸診
出血の可能性が高い場合には、まず直腸診を行います。
手袋をして麻酔のゼリーを塗布し、肛門から挿入して触診します。
この診察で、痔の有無や腫れ、腫瘍などを確認し、必要に応じて直腸鏡で直腸粘膜の状態を詳しく観察します。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)
直腸から大腸全体、小腸の大腸寄りの部分の粘膜を直接観察し、組織採取によって確定診断を行う検査です。
この検査により、大腸がんやその前段階である大腸ポリープなどの病変を早期に発見することができます。
また、検査中にこれらの病変を切除する日帰り手術も行うことができます。
このように、大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)は病変の状態を詳細に確認できるため、早期発見と治療に大きく貢献しています。
血液検査
炎症の程度や出血による貧血の有無を調べるために行われます。
消化器疾患でお困りごとは当院へ
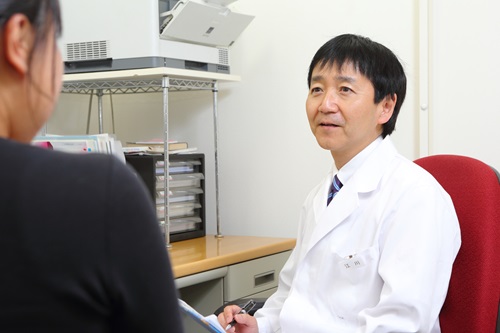
-
奈良市の江川消化器内科医院は、ひとりでも多くの患者さんの病気の早期発見・治療し、健康で充実した人生をサポートする医療機関を目指しております。
日本内科学会認定内科専門医、日本消化器内視鏡学会指導医・専門医の医師が、丁寧かつ正確に診断を行い、適切な治療を行います。消化器の症状でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。